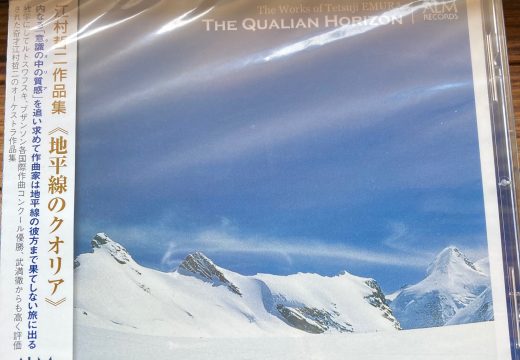※『豊田喜代美ソプラノリサイタル』ピアノは小坂圭太氏。(小坂圭太 略歴:東京藝術大学音楽学部附属音楽高校、同大学音楽学部を経て、1987年同大学院修士課程を修了。85年、第54回日本音楽コンクール(ピアノ部門)入選、89年、第58回同コンクール声楽部門でコンクール委員会特別賞(協演賞)。在学中より、ソロ・伴奏・室内楽・オーケストラの鍵盤楽器・コレペティートゥアなど多岐に亘る活動を開始、サントリー音楽財団、アリオン音楽財団などが主催するフェスティヴァルやNHK-FMなどに度々出演している。現在、お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科准教授、愛知県立芸術大学音楽学部、相愛大学音楽学部でも後進の指導にあたっている。)
『声楽に導いた歌うピアノ 』(日本歌唱芸術協会会報より転載し加筆いたしました)
私はピアノを弾くのが好きで、小学校卒業時に記した、将来なりたいものは「ピアニスト」でした。5歳でピアノを習い始めてから、モーツァルト、J.S.バッハ、ベートーヴェンなど、各作品のレッスンを受けており充実していました。ピアノの発表会には祖母や家族が来てくれた嬉しい思い出があります。
しかし中学生時にバレーボールクラブに入り、私の父親がバレーボール選手・監督を歴任している専門家であったこともあり、その指導を受けて面白くなりました。その時に、腹筋と背筋の身体トレーニングの有効性と「今から続けておくと良い。」と父から教えられ、その時からドイツに留学するまで毎日就寝前に腹筋・背筋のトレーニングをしていました。バレーボールの試合と早朝練習に明け暮れ、よく突き指をしてレッスンを休みがちになり、ほぼ3年間、ピアノのレッスンを止めていました。ピアノの技術面のトレーニングは遅れてしまいましたが、この時期に運動に集中できたことは基礎体力作りになった可能性があると思っています。
桐朋学園女子高等学校普通科(別に音楽科がある)は幼稚園からそのまま上がってきた学生がほとんどで、私は高等学校から入試を受けて入学し、仲良し6人グループの内、私を除いた5人が音楽大学志望者でしたので、何となく私も音大を受験することにし、高校2年生からピアノのレッスンを受けることを再開しました。この友達との学園生活が私を音楽の道に載せてくれたのだと思います。
学園祭では、6人それぞれが詩を書いてそれに作曲をしピアノを弾きながら歌って発表するという音楽発表会を企画しました。当日は家族、親戚一同の他、先生方や友人知人で教室はいっぱいになり、驚きました。自作品の説明をして、その曲を自らピアノ伴奏して歌うという一生懸命の発表に、あたたかな拍手をいただいたことを覚えています。他に特に心に残っているのは、体育祭の徒競走選手に選抜されてグランドで練習の最中にコーラス部から呼びに来て音楽の林先生の指揮での合唱練習の中に入って歌ったことです。体操着のまま急に入って歌う私を皆は全く気にせず合唱していました。その時、初めて皆と響き合う声の美しさを体感し、合唱が大好きになりました。
音大受験勉強を高校3年5月から始め、5才から10才まで指導を受けた聴音ソルフェージュを再開し、楽典、コ―リューブンゲンやイタリア歌曲の勉強を開始し、桐朋学園芸術短期大学音楽科に入学して勉強が本格化しました。桐朋学園大学のピアノ科2学年に編入希望しており、当時指導を受けていた2人のピアノの先生が、それぞれ、井口基成先生(桐朋学園大学レッスン室でベートーヴェン作曲ソナタ)と、江戸弘子先生(ご自宅でラヴェル作曲ソナチネ)のレッスンに連れて行ってくださり、井口先生、江戸先生から同じ評価の「音楽的。特に音質が美しい。」と言われて自信を持ち、一日8時間の練習も苦にならず、編入学に必要な受験曲も準備万端でした。それが声楽家に憧れるようになったきっかけは、やはりピアノの素晴らしさ~歌うピアノとの出会いでした。
芸術短大の当時のカリキュラムは声楽とピアノを同等に学習することに定められており専攻に分かれていませんでしたので、全員が声楽およびピアノのプロフェッショナルに指導を受けました。「声楽とピアノは音楽の基本として同等」というようなことが創立時の理念、と聞いています。私はこの理念に育てられたのだな、と思っています。
高校三年5月から音大受験のための副科声楽指導を受けていた萩谷納先生は、芸術短大と桐朋音大両方の声楽教授でした。入学して声楽の本格的な指導を受け、自分の情感を歌声と言葉で表現するという音楽の世界があることに驚きました。ほとんどの声楽作品には詩があります。詩へのアプローチは、それまでにない精神世界を感じ、それを歌声に表す「声楽」の勉強に興味が掻き立てられ、練習に没頭しました。
萩谷納先生のピアノ伴奏は、ピアノが歌っているという形容がぴったりでした。今でも覚えている一番最初のレッスン曲はイタリア歌曲のPiacer d’amorでした。レッスンの度に、私は歌うピアノに誘われて一緒に歌っていく演奏の醍醐味に魅せられていきました。それが自分にとってかけがいのない素晴らしい創造の世界に導くものだと確信した時、瞬間的に、萩谷先生に「私は声楽家になりたいと思います。」と、自分勝手に声楽科への編入を決めてしまい、ピアノの先生には申し訳ないことになってしまったと思っています。その時のピアノの先生に、大学卒業時に読売新人演奏会に大学の声楽代表として出演することのご報告をした時には、「声楽科に入って良かったですね」と仰ってくださいました。
今も、ピアノ伴奏を自ら弾きながらピアノと歌うことは、私にとっては、良い演奏に向かうために必要なことになっています。楽譜のピアノ部分には和音が記されており、和音の響きは旋律の求める色彩が込められているように感じます。
現在、私達がピアノと呼んで親しんでいるのは、19世紀以降に制作されたもので、17,8世紀にバルトロメオ・クリストフォリが製作した強弱機能の有るチェンバロであるClavicembalo col piano e forteがピアノと呼ばれる最初のものです。現代においてピアノの正式呼称はフォルテピアノですが、「古楽器」という分野がはっきりしてきた20世紀以降、19世紀以降のピアノをモダンピアノと呼び、18世紀以前から19世紀前半以前のフォルテピアノと区別するようになりました。
また作曲家のジョン・ケージ(1912-1992)が自作品の演奏に際し、必要にせまられ1940年に発案したプリペアドピアノは、主に現代曲演奏に用いられています。
大音量と劇的な表現力で協奏曲などをオーケストラと共演するモダンピアノと古楽器のフォルテピアノとでは、その味わいは異なっていることは容易に解ります。
例えば、シューべルティアーデ(シューベルトを囲んで彼の作品や新作歌曲発表などを行うサロンコンサート)のような、特に歌曲演奏会を住居の部屋など小空間で催す場合には、フォルテピアノは歌声と共に、深遠で親しみのある演奏を実現するのではないか、と思います。シューベルトを囲んで主に歌曲を演奏していた集まりは、その精神が尊ばれ、現在、オーストリアのシュヴァルツェンベルクで定期開催され、ウィーン国立歌劇場で主役を歌った歌手を、同時期に開催されるシューベルティアーデでの歌曲リサイタルや室内楽などの演奏でも聴くことが多いです。
ショパンはプレイエルとエラールを愛用していたことは知られており、エラールはフランス人で1777年に初めてピアノを製作しました。当時、ハイドン、ベートーヴェン、リスト、メンデルスゾーン、ヴェルディ、ワーグナー、フォーレ、ラヴェルなども使用していました。
私がモダンになる前のプレイエルの伴奏でシューマンの歌曲を演奏した時には、まるで庭の樹木と歌っているような、身近であたたかな音色に触発されて歌いました。忘れられない感覚でした。ピアニストはご自分で、何回も調律していました。
ショパンが生きていたら、エラールとプレイエルの音色をどう感じていて、何が好きだったのかを聞いてみたいです。
次にピアノ(モダンピアノ)のメカニズムについて確認したいと思います。
ピアノのメカニズム:ピアノは、鍵盤を押すとテコの原理でハンマーが跳ね上がり、弦をたたいて音が出るというメカニズムを共鳴箱に収めたものです。それゆえ、猫が鍵盤の上を歩いても、ホロヴィッツが弾いても音そのものは同じであると、しばしば言われます。しかし、その一方で、たとえば東京のオーケストラの定期演奏会などで、同じホールの同じピアノで、同じ作曲家の作品(時に同じ曲)を演奏し、しかも同じ席で聴いているにもかかわらず、ピアニストが異なると、かなり違った音に聞こえることも私たちは経験しています。そこで、ピアノの音の違いがどのようにして起こるのかという問題を考えてみたいと思います。
ピアノの音の違い:最初に、論考の前提としてピアノの音は「つくられる」ものだということを確認したいと思います。先ず演奏会の前に必ず行われる整調、調律、整音でどのようなことがなされるのかを整理します。
・整調:整調とは、鍵盤とハンマーのアクションを調整することです。つまりピアニストの好みや演奏曲目に合わせて、タッチを軽くしたり、重くしたり、あるいは、ハンマーと弦の距離を調整したり、鍵盤がどの位降りたらダンパーが上がり始めるかのタイミングを調整することです。この作業により、ハンマーが弦を打つ速度vが調整されることから、鍵盤に同じ質量mがかかっても(同じ力で鍵盤を押しても)
E= 1 / 2/m v から、弦を打つハンマーのエネルギーが調整されることにより、少なくとも音量は変化することになります。それゆえ、同じピアノでも異なる整調を行えば音は違ってきます。
・調律:弦の振動数の比が2:1になれば1オクターブ(8度)の音程差が生じ、3:4になれば5度、4:3になれば4度、4:5になれば長3度となります。調律は弦の張力を加減して、振動数を調整することです。ところで、このような音程差の組み合わせで8度の中に12の音を割りふると、和音が美しく響くものと混濁するものができます。ピアノの様に弦の張力や長さを自由に変えられない楽器では、どこかにつじつまを合わせる必要があります。声楽や管弦楽器ではこの点は演奏の際に容易に改善できます。
そこで、オクターブの中の12の音の音程差を、原理上2の12乗根で均等に割り振ったのが、今日ピアノの調律として一般的な平均律です。しかし、この調律法はあくまでつじつま合わせですので、オクターブ以外の和音はどこか味気ないものになります。この方針も演奏者が決定するものですから、同じ作品を同じ楽器で演奏しても平均律で通す場合と、微妙な色付けを行うのでは、極端なほどの聴感上の差異を感じます。そして、この選択肢が、演奏者の作品解釈の重要な要素にもなります。
・整音:整音の最も重要なポイントは、ハンマーの硬さを調節することです。ハンマーはフェルトでできていますので、フェルトを膨らませたり圧縮させたり、表面を多少毛羽だたせたり、すっきり削ったりすることによって、音は劇的に変化します。そのことは、太鼓の ばち を硬いものにするか、柔らかいものにするかで、同じ力でたたいても音がずいぶん違うことから、容易に理解できます。以上の作業は、プロフェッショナルな演奏家とピアノ技術者の間で演奏会の前に入念な検討を経て行われるものであり、同じピアノでも演奏者が変われば音が違ってくるのは当然であり、また、同じピアノ、同じ演奏家でも、演奏する作品の作曲者の時代やドイツ、フランスなど国籍の違いで音を変えるのは当然のことと言えます。さらに、ピアノの場合はペダルの存在を無視することができません。ペダルには音の持続時間を変化させる操作(ラウドペダル、右のペダル)と、通常3本セットである弦のうち、2本のみを打弦して音色・音量の変化をもたらす操作(ソフトペダル、左のペダル)、特定の音だけを持続させる操作(ソステヌートペダル、真ん中のペダル)の3種類があります。
作曲家が、現在のピアノの機構が確立されて以降の時代の場合は、さほど問題はありませんが、現在のピアノの機構以前の時代の場合は、ペダルの使用は当時の楽器の響きを念頭に置いて演奏家が判断する必要があります。そのために、同じピアノで同じ作品を演奏しても、ピアニストによって、響きの変化が生じる場合があります。
ここまで、主にピアノの機構面に即して音色の変化がどのように起こるのかについて述べましたが、ここで、ピアニストの身体をとおしてどのような音色変化ができるのかについて述べてみたいと思います。
ピアニストの身体と音色の変化:ピアニストは鍵盤の押さえ方について、しばしば指を立てたり寝かせたり、微妙に異なる方法で鍵盤を弾きます。しかし音色は指先や手の具合だけでなく、それらに繋がっている骨格や筋肉、身体全体で創られるものです。そのことを知識だけでなく、体感によっても深く理解し自覚することが重要であると思います。このメカニズムの知識と体感による自覚の重要性は、身体そのものが楽器である声楽にとって顕著といえると思います。
ウィーンに在るベーゼンドルファーのピアノ工房にはホールがあり、発表会や演奏会で使用されています。筆者が個室を借りて声楽練習を終えた帰り際に見たのは、そのホールで行われているピアニストの公開レッスンでした。ウィーン音大などの受験前の若い人たちが受講していました。
そのピアニストは、ピアノの構造を説明し、受講生がその知識を持っているか否かを確認していました。また、ピアノを弾く際の人間の骨格がどうなっているかについて、図を用いて全身について説明し、椅子と臀部の接着面について、自らをモデルに解説しました。受講生4名に対してそれぞれに、「自分の中心がどこにあるか」を聞いていましたが、「どこにあるのが正しい」とは言わず、受講生に自分の中心を意識するように伝えて1フレーズを弾かせ、中心の位置を受講生に確認しながら、「そう。その音色だ!」と指導していました。この「自分の中心」は身体だけでなく精神も含んでいる、と私なりに解釈しました。受講生はその音色を出した姿勢を記憶したと思います。一人の受講生は息を止めないようアドバイスされていました。
受講生は4名で、3人は1分ほどで止められ、作品を演奏するにあたり読むべき本を3冊教えられ、それを読んだら、また来なさい、とのことでした。あと1人は最後まで弾くことができ、アフェクト(情念)という言葉を多く用いての表現について詳細に指導を受けていました。その曲の文化的背景の理解が演奏に必要なのは、同じ人間として生きていることを知って自分のものとしてその曲の本質を魂で感じ取るためと私は自分なりに解釈しました。
「真にアフェクトを感じると自分の中心が燃えて、弾くエネルギーとなる、自分の中心が燃えていることを感知できければならない、そのために本を読むのだ」とのことでした。哲学の講演のような内容のある公開レッスンでした。
この経験で、1999年からの大学院大学(JAIST)入学で開始した「芸術の人への作用」のキーワードが、個別の心身における感受性であることが確信でき、沖縄県立芸術大学赴任後、新授業「身体知基礎演習」を立ち上げるきっかけとなりました。
授業「身体知基礎演習」は音楽学部全専攻から履修生が来ており、毎年の授業評価において、履修生全員が自らの専門のパフォーマンスが向上したという評価を得ました。この全員であることが、とても嬉しく、誇りに思います。その履修生のお一人だった根神夢野さん(本協会幹事)は、NSCA-CPT(注1)の資格を近年取得しました。徐々に若い人たちにも身体が楽器である歌唱についての意識が深まっているならば、大変嬉しく思います。(注1)NSCA(National Strength and Conditioning Association/全米ストレングス&コンディショニング協会
声楽とピアノで創る音楽芸術の極みとされるドイツ歌曲…。2004年に浜離宮朝日ホールにおいて「シューベルト女声リートの世界~詩・ゲーテ~」を開催しました。シューベルトゆかりの地で、最初の墓地の在ったウィーンのペッツラインドルフに住んで、ピアニストのヴォルフガング・フックスベルガーの許で準備をしてリサイタルに臨みました。
特に最近、ドイツ歌曲リサイタルを演奏会案内で見ることが少なくなったように思います。
2023年10月28日(土)ドイツ歌曲珠玉の作品第3回「仲本博貴バリトンリサイタル(那覇市パレット市民劇場)」でシューベルトの歌曲が歌われるのは素晴らしいと、喜んでおります。このリサイタルチラシを見てお気づきの方も多いと思いますが、声楽家・仲本博貴のリサイタルでありながら、ピアニスト・内海博子(2024年1月現在ウィーン音楽大学マスタークラス留学中)の名前表記が同列で大きさがほぼ同じです。これは、ドイツ、オーストリアなどのドイツ歌曲演奏会では普通のことで、それは、ドイツ歌曲演奏においては歌手とピアニストは同等の責任を負っているソリストであるということを示しており、今回も仲本氏の判断だと思います。
ドイツ、オーストリアなどの音大には歌曲伴奏科があり、沖縄県立芸大卒の内海博子さんはミュンヘン音大も修了し、指導側としても勤めています。また、本協会のドイツ歌曲マスタークラスでは、世界的歌曲ピアニストの演奏家でウィーン音大教授との出会いにより、ヨーロッパで更なる活躍が約束されています。
私も先のドイツ歌曲リサイタルから11年経過した分の情感が満ちてきているのを感じるのでドイツ歌曲を歌いたいと思っています。ドイツ歌曲演奏の準備は、私にとっては、自分が全身全霊で作品に向かっているかを問い続けながら、身体を楽器として鍛える機会になると思います。
歌唱における人への作用を、音楽療法の観点と身体運動科学の視点を持って、特に1999年から研究し実践しています。身体全体と精神全体とで詩と歌を歌うという行為は、ある意味、自分の心身も他人の心身も良好にすると考えております。音楽家とだけでなく、機会あるごとに、子供たち、人々と、歌を通して交流していきたいと願っております。
声楽家だけでなく、全ての音楽家にとってもピアノはなくてはならないパートナーであると思います。今でも、ピアノについて少しでも知りたいと、思い続けております。ピアノに関する筆者の疑問を、即、解決くださったピアニストの渡辺健二氏に感謝申し上げます。